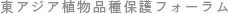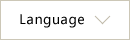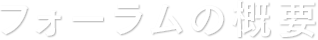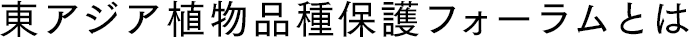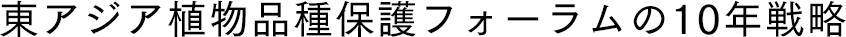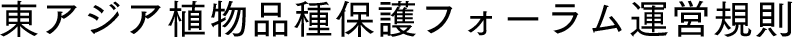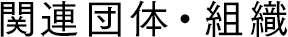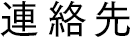東アジア植物品種保護フォーラムは、ASEAN Plus Three(中国、日本、韓国)で構成され、
全フォーラムメンバーのUPOV加盟に向け、各国でUPOV条約に則した効果的な植物品種保護
(PVP)制度を構築することにより、東アジア地域におけるPVPの調和と協力を進め、
農業の持続的発展及び食料安全保障に貢献することを目的として、2007年に設立されました。
2017年9月11日にミャンマーのネピドーにて開催された第10回東アジア植物品種保護フォーラム年次会合において、フォーラムのこれまでの実績及び今後の可能性について検討し、東アジア植物品種保護フォーラムの「10年戦略」について話し合い、準備を行うことが採決されました。
各フォーラムメンバー国間で8か月間にわたり「10年戦略」案の検討と議論が行われ、2018年8月1日にフィリピンのムンティンルパにて開催された第11回東アジア植物品種保護フォーラム年次会合において、「東アジア植物品種保護フォーラム10年戦略(2018-2027)」及び「東アジア植物品種保護フォーラム運営規則」が採択されました。
さらに2019年4月22日に中国北京において開催された第12回東アジア植物品種保護フォーラム年次会合において、「東アジア植物品種保護フォーラム10年戦略(2018-2027)」及び「東アジア植物品種保護フォーラム運営規則」は一部改定されました。

“長期方針”
全フォーラムメンバーのUPOV加盟に向け、各国でUPOV条約に則した効果的な植物品種保護(PVP)制度を構築することにより、東アジア地域におけるPVPの調和と協力を進め、農業の持続的発展及び食料安全保障に貢献する。
“目標”:今後10年で達成すべき目標
-目標1:各国がUPOV条約に則してPVP制度を強化し、植物育種への投資を促進
-目標2:UPOVへの加盟支援、出願・審査手順の調和の促進、地域における効率的なPVP協力の強化に貢献
“コア活動”
– 各国個別活動:目標1の達成に向けた活動
- UPOV事務局支援の下、国内PVP法規則を整備
- 出願から育成者権付与までのPVP制度履行のため、国内行政手続を整備・強化
- 審査能力を強化
- DUS審査基準を発展
- 関係機関、政策決定者及び利害関係者に対するUPOV制度の意識啓発
(UPOV制度やそのメリット等への理解) - 効果的なPVP制度促進に向け官民連携を強化
– 地域協力活動:目標2の達成に向けた活動
- UPOV条約に基づくDUS審査基準開発への協力
- 調和のとれた申請と審査手続開発への協力
- 研修や、PVP制度運営、DUS審査の経験共有に関する協力
- 効果的な執行に向け効果的な取組を共有
地域協力活動は複数のフォーラムメンバーあるいは全メンバーの協力によって効果的な方法で実施
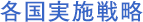
各フォーラムメンバー国は、上述の共通方針を反映した国内戦略として、各国実施戦略を作成する。各国実施戦略には、各メンバー国の状況に応じた国内活動の他、地域協力活動も含めることができる。各メンバー国は定期的にその合意に基づいてその個別の実施戦略を更新でき、他のメンバー国との共有が奨励される。
- 国内目標 (今後10年)
- 目標(課題を分析の上(今後3年))
- 予定される活動 (今後3年)
- 工程表
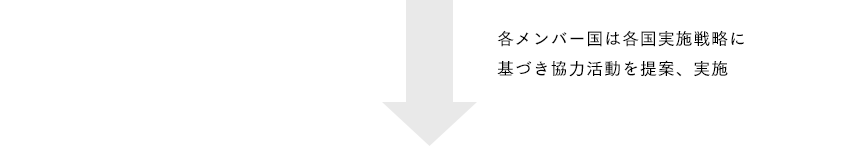
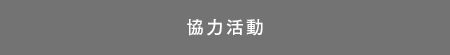
10年戦略の”共通方針”に沿った活動を優先
東アジア植物品種保護フォーラム運営規則(ROP)は第11回年次会合で採択され、第12回年次会合で一部改定されました。
ROPは、全てのメンバー国及びゲストが東アジア植物品種保護フォーラムの協力活動及び関連する活動の実施及び年次会合の運営を行う上での指針とするため作成されました。ROPは今後実施されるすべてのフォーラム活動に適用されます。但し、事情や状況に応じて対応が変わる可能性は認められています。
毎年メンバー国から提案されるフォーラムの協力活動(特に資金援助を要する活動)は、東アジア地域のPVP制度のさらなる調和及び/又は統合を目的とし、10年戦略の共通方針に沿ったものとする必要があります。
2007
| 10月 | |
|---|---|
| アジア地域の植物品種保護制度に係る協力と協調に関するワークショップ 東アジア地域各国政府・機関の代表者が、植物品種保護制度の強化に向けて意見交換を実施。その際、日本から提案した「東アジア植物品種保護フォーラム」の設置について支持が得られ、各国がこの分野で今後も協力していること等を内容とする共同ステートメントを取りまとめた。 |
日本 |
| 11月 | |
| 第7回東南アジア諸国連合(ASEAN)プラス3(日中韓)農林水産大臣会合「東アジア植物品種保護フォーラム」の設置を了承。 | タイ |
2008
| 6月 | |
|---|---|
| オランダ植物品種保護研修への参加(インドネシア) | オランダ |
| 7月 | |
| 東アジア植物品種保護フォーラム 第一回会合 | 日本 |
| 8月 | |
| 受入研修1「基礎研修」 | 日本 |
| 10月 | |
| 受入研修1「基礎研修」 | オランダ |
| 11月 | |
| 第1回審査基準と審査・栽培試験方法の調和に係る技術研修会(ワークショップ) | インドネシア |
| APECセミナー「植物品種保護」 | インドネシア |
| 受入研修2「短期専門技術研修」 | 日本 |
| 12月 | |
| ベトナム国内研修 | ベトナム |
| 第3回植物品種保護に関する国内セミナー | インドネシア |
| ベトナム植物品種保護制度に関する意識普及・啓発国際セミナー | ベトナム |
2009
| 1月 | |
|---|---|
| 受入研修3「長期専門技術研修」 | 日本 |
| イネの審査規準調和に関する専門家会議 | フィリピン |
| 2月 | |
| タイ国内研修 | タイ |
| DNA品種識別のための日中韓専門家会合 | 中国 |
| アグロネマ審査基準作成に関する専門家会合 | タイ |
| 3月 | |
| シンガポール国内研修 | シンガポール |
| マレーシア国内研修 | マレーシア |
| 4月 | |
| 東アジア植物品種保護フォーラム 第二回会合 | 中国 |
| 5月 | |
| インドネシア国内研修 | インドネシア |
| トウガラシ(Capsicum)審査基準の調和に関する専門家会議 | インドネシア |
| 6月 | |
| インドネシア-オランダ合同セミナー(農作物部門) | インドネシア |
| インドネシアDUSテスト研修 | インドネシア |
| 8月 | |
| 第2回審査基準と審査・栽培試験方法の調和に係る技術研修会(ワークショップ) | タイ |
| 受入研修1「基礎研修」 | 日本 |
| 「植物品種保護制度のもたらす影響とその効果」に関する国際シンポジウム | 韓国 |
| 10月 | |
| 受入研修2「短期専門技術研修」 | 日本 |
| 11月 | |
| 受入研修3「補完研修」 | 日本 |
| マレーシア植物品種保護制度意識向上セミナー | マレーシア |
| ベトナムDUSテスト研修 第一回 | ベトナム |
| ベトナムDUSテスト研修 第二回 | ベトナム |
| 12月 | |
| ベトナムDUSテスト研修 第三回 | ベトナム |
2010
| 2月 | |
|---|---|
| 植物品種保護制度とその経済効果に関する意識啓発セミナー | シンガポール |
| 3月 | |
| 審査官業務研修 | 日本 |
| トウガラシ(Capsicum)およびアグラオネマ(Aglaonema)の審査基準の調和に関する専門家会議 | 日本 |
| UPOV・DUSテストセミナーへのフォーラム参加国の招へい | スイス |
| 4月 | |
| 植物品種保護制度と農業者の権利及び利益に関する国際セミナー | 中国 |
| 東アジア植物品種保護フォーラム 第三回会合 | 韓国 |
| 「公的機関における品種保護制度利用の取り組み」に関する国際セミナー | 韓国 |
| 7月 | |
| 植物品種保護・審査制度に関する国際研修 | 韓国 |
| 第4回植物品種保護制度に関する国内セミナー | インドネシア |
| ドリアン、パパイヤ、モカラ審査基準作成に関する専門家会合 | タイ |
| 8月 | |
| トウガラシ(Capsicum)およびアグラオネマ(Aglaonema)の審査基準の調和に関する専門家会議 | マレーシア |
| 第3回審査基準と審査・栽培試験方法の調和に係る技術研修会(ワークショップ) | マレーシア |
| 受入研修1「基礎研修」 | 日本 |
| 9月 | |
| 植物品種保護制度の意識啓発・普及セミナー | タイ |
| 11月 | |
| 受入研修2「短期専門技術研修」 | 日本 |
| インドネシア国内研修 | インドネシア |
| マレーシア国内研修 | マレーシア |
| 第5回植物品種保護(PVP)に関する国内セミナー | インドネシア |
2011
| 1月 | |
|---|---|
| 受入研修3「要人研修」 | 日本 |
| 2月 | |
| 東アジア地域で調和されたイネの審査規準を用いたロードテスト実施に関する会議 | フィリピン |
| UPOV基礎技術に関するセミナー及びUPOVに調和した審査基準作成方法に関するワークショップ | フィリピン |
| 3月 | |
| 受入研修4「審査官業務研修」 | 日本 |
| 中国国内審査基準作成研修 | 中国 |
| 5月 | |
| 東アジア植物品種保護フォーラム 第4回会合 | インドネシア |
| 6月 | |
| DUSテストおよび審査基準の調和に関するワークショップ | タイ |
| 9月 | |
| マレーシア高度な栽培試験研修1 | マレーシア |
| 第4回審査基準と審査・栽培試験方法の調和に係るワークショップ | タイ |
| 10月 | |
| アジア種子産業の発展に関する国際ワークショップ | 韓国 |
| 受入研修1「担当者短期専門技術研修」 | 日本 |
| 11月 | |
| UPOV技術作業部会開催に係る東アジア植物品種保護フォーラム国のオブザーバー参加 | 日本 |
| 12月 | |
| 中国国内審査基準作成会議及びワークショップ | 中国 |
2012
| 1月 | |
|---|---|
| 受入研修2「要人研修」 | 日本 |
| 2月 | |
| フォーラム関係国会議 | タイ |
| キャッサバ審査基準作成に関する専門家会合 | タイ |
| オイルパーム審査基準作成に関する専門家会合 | マレーシア |
| カンボジア意識啓発セミナー | カンボジア |
| パパイヤ、カプシカム審査基準作成に関する専門家会合 | インドネシア |
| 3月 | |
| マレーシア高度な栽培試験研修2 | マレーシア |
| モカラ審査基準作成に関する専門家会合 | シンガポール |
| 7月 | |
| タイ 植物品種保護制度 に関わる情報処理システムに関する研修 | 日本 |
| 9月 | |
| DUS審査における写真撮影研修 | タイ |
| 10月 | |
| 東アジア植物品種保護 フォーラム ハイレベルスタディツアー | 日本 |
| 短期専門技術研修 | 日本 |
| 12月 | |
| オイルパーム審査基準作成に関する専門家会合 | マレーシア |
2013
| 2月 | |
|---|---|
| ドリアン、パパイヤ審査基準作成に関する専門家会合 | フィリピン |
| キャッサバ審査基準作成に関する専門家会合 | インドネシア |
| モカラ審査基準作成に関する専門家会合 | タイ |
| 7月 | |
| 東アジア植物品種保護フォーラム テクニカルワーキンググループ会合 | マレーシア |
| 第6回東アジア植物品種保護フォーラム年次会合 | マレーシア |
| 東アジア植物品種保護シンポジウム:植物品種保護の国際調和に向けた地域間協力について | マレーシア |
2014
| 8月 | |
|---|---|
| 第7回東アジア植物品種保護フォーラム年次会合 | ラオス |
| 東アジア植物品種保護フォーラムシンポジウム | ラオス |
| 9月 | |
| イネのDUSテスト研修 | ベトナム |
| 11月 | |
| ランブータン、スターフルーツ審査基準作成に関する専門家会合 | マレーシア |
2015
| 2月 | |
|---|---|
| デンドロビウム審査基準作成に関する専門家会合 | 韓国 |
| 9月 | |
| 第8回東アジア植物品種保護フォーラム年次会合 | 韓国 |
| 第8回東アジア植物品種保護フォーラムシンポジウム | 韓国 |
| アカシアのテストガイドライン調和に関する第1回会合 | マレーシア |
| 10月 | |
| インドネシア専門家受け入れ研修 | 長崎 |
| 11月 | |
| 育成者権保護制度の運営についての現地調査 | タイ |
| イネの栽培試験研修 | マレーシア |
| トマトの栽培試験研修 | ベトナム |
| 12月 | |
| UPOV条約にもとづく植物品種保護の啓発ワークショップ | ブルネイ |
| UPOV条約にもとづく植物品種保護の啓発ワークショップ | ラオス |
| UPOV条約にもとづく植物品種保護の啓発ワークショップ | カンボジア |
2016
| 1月 | |
|---|---|
| ブルネイでUPOV条約にもとづく植物品種保護の啓発ワークショップが開催されました。 | ブルネイ |
| ラオスでUPOV条約にもとづく植物品種保護の啓発ワークショップが開催されました。 | ラオス |
| カンボジアでUPOV条約にもとづく植物品種保護の啓発ワークショップが開催されました。 | カンボジア |
| 2月 | |
| UPOV加盟を見据えた国際調和にかなうPVP法起草支援 | マレーシア |
| 7月 | |
| 植物品種保護に関するASEAN諸国高官スタディーツアー | 日本 |
| 8月 | |
| トウモロコシの栽培試験に関する研修 | ベトナム |
| 9月 | |
| 第9回東アジア植物品種保護フォーラム年次会合 | ベトナム |
| UPOV条約下での植物育成者権行使に関するセミナー | ベトナム |
| 11月 | |
| 育成者権保護制度の運営についての現地調査 | マレーシア |
| 12月 | |
| UPOV条約にもとづく植物品種保護の啓発セミナー | ミャンマー |
2017
| 1月 | |
|---|---|
| マリーゴールドの栽培試験に関する研修 | タイ |
| Naktuinbouw主催植物品種保護制度技術研修に講師を派遣 | ミャンマー |
| 2月 | |
| UPOV条約にもとづく植物品種保護の啓発セミナー | タイ |
| 7月 | |
| カンボジアでトマトの栽培試験に関する第1期研修を開催 | カンボジア |
| 8月 | |
| 国内啓発セミナーをベトナム・ホーチミンにて開催 | ベトナム |
| 9月 | |
| 第10回東アジア植物品種保護フォーラム年次会合をミャンマー・ネピドーにて開催 | ミャンマー |
| 国内啓発セミナーをミャンマー・ネピドーにて開催 | ミャンマー |
| 10月 | |
| カンボジアでトマトの栽培試験に関する第2期研修を開催 | カンボジア |
| ブルネイとミャンマーの植物品種保護法について、植物新品種保護国際条約(UPOV条約)との適合性が認められました。 | ブルネイ / ミャンマー |
| 11月 | |
| ミャンマー農業畜産灌漑省担当官によるベトナムにおけるPVP制度研修を開催 | ミャンマー / ベトナム |
| 国内啓発セミナーをベトナム・タイグエン市にて開催 | ベトナム |
2018
| 1月 | |
|---|---|
| 植物新品種保護セミナーを中国・杭州にて開催 | 中国 |
| ミャンマーにてトウモロコシの栽培試験に関する研修を開催 | ミャンマー |
| 7月 | |
| バレイショDUSテスト研修をインドネシアにて開催 | インドネシア |
| 8月 | |
| 第11回東アジア植物品種保護フォーラム年次会合をフィリピンにて開催 | フィリピン |
| UPOV条約にもとづく植物品種保護の国際セミナーをフィリピンにて開催 | フィリピン |
| 植物品種保護システムの国際調和に関する法的コンサルテーションをマレーシアにて実施 | マレーシア |
| 12月 | |
| UPOV条約にもとづく植物品種保護の国内啓発セミナーをラオスにて開催 | ラオス |
2019
| 1月 | |
|---|---|
| 主要作物の標準品種データベース構築ワークショップをミャンマーにて開催 | ミャンマー |
| 4月 | |
| 植物品種保護の国際セミナーを中国にて開催 | 中国 |
| 東アジア植物品種保護フォーラム第12回本会合を中国にて開催 | 中国 |
| 7月 | |
| PVPの先進事例を学ぶため3ヶ国の高官がベトナムを訪問 | ベトナム |
| 9月 | |
| ベトナム中南部海岸エリアにおける植物品種保護セミナーをダナンにて開催 | ベトナム |
| 10月 | |
| トマトのDUS研修をミャンマーにて開催 | ミャンマー |
| 11月 | |
| ベトナム中部高原エリアにおける植物品種保護セミナーをダラットにて開催 | ベトナム |
| 12月 | |
| トウモロコシのDUS研修をカンボジアにて開催 | カンボジア |
2020
| 11月 | |
|---|---|
| 東アジア植物品種保護フォーラム第13回本会合を開催 | ベトナム |
| ベトナム農業農村開発省が「植物品種保護に関する国際セミナー」を開催 | ベトナム |
2021
| 1月 | |
|---|---|
| ニガウリのDUSテスト研修をオンラインで実施 | ベトナム |
| 3月 | |
| トウモロコシのDUSテスト研修をオンラインで実施 | インドネシア |
| 8月 | |
| 東アジア植物品種保護フォーラム第14回本会合を開催 | 日本 |
| 9月 | |
| 農林水産省主催で「植物品種保護に関する国際セミナー」(オンライン)を開催 | 日本 |
2022
2023
2024
| 2月 | |
|---|---|
| 日本 農林水産省が農家の自家増殖に関するオンラインワークショップを実施 | 日本 |
| 9月 | |
| 東アジア植物品種保護フォーラム第17回年次会合を開催 | カンボジア |
| 農業の発展における植物品種保護の役割に関する国際セミナーをカンボジアにて開催 | カンボジア |
2025
2026
Community Plant Variety Office (CPVO)
- 農林水産省
- 食料産業局知的財産課種苗室
E-Mail : jpvp@maff.go.jp
電話:03-6738-6444
- 東アジア植物品種保護フォーラム 事務局
- 公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会 (JATAFF)
HP:http://Jataff.or.jp/index.html
E-Mail: st-pgr@jataff.or.jp
電話:03-3509-1161